こんにちは。マチ弁のワタルです。
今回紹介する本は「スゴイ!行動経済学」です。
いきなりですが、「マリッジブルー」ってご存じですか?
結婚式が近づくにつれてパートナーとのケンカが増えて「この人とやっていけるのか?」と不安に襲われ、気分が落ち込んだりする症状ですよね。そして、結婚後もなかなか解消されない人も多いそうです。
「マリッジブルー」になるのは女性が多いといわれていますが、男性も少なくないそうです。
結婚を決めた時点では、幸せな将来を誓い合ったパートナーなのに、なぜか結婚式が近づくとケンカが増えてしまいます。そのことが原因で早期に離婚してしまうカップルも少なくありません。
これは、今後、結婚を考えている人にとっては、見過ごせないことですよね。
でも、大丈夫です。
その問題、「行動経済学」で解決できます。
「行動経済学」とは、簡単にいうと、人の心の裏側を研究する「心理学」とお金や損得を扱う「経済学」を合わせた学問です。
「マリッジブルーと関係ねーじゃん。」
と思った方、そう結論を急がないでください。もう少し、説明させてください。
人は完全に合理的な行動をするのではなく、ときに不合理な行動や判断をするものです。
例えば、次のような行動です。
・つまらないものでも一度手に入れたらなかなか手放せない
・罰金を払えば悪いことをしても良いと考える
・ギャンブルで手に入れたお金は簡単に浪費してしまう
・健康に悪いと分かっている食べ物をやめられない
いかがですか?
心当たりありませんか?
つまらないものは捨てる、罰金を払っても悪いことはしてはいけない、ギャンブルで手に入れたお金も一所懸命働いて得たお金も価値は同じ、健康に悪いと分かっている食べ物だったら食べない、このように考えるのが合理的ですよね。
でも、人は不合理な行動や判断をしてしまうものなのです。
そして、世界最前線の研究により、人の不合理な行動や判断には一定の法則性があることが分かっています。
その「人の行動や判断の法則」を研究する学問が「行動経済学」なんです。
「行動経済学」を知ることで、人への理解が深まるだけでなく、「人にやさしくなれる」のです。
実は、「マリッジブルー」も「人の行動や判断の法則」が原因で起こるものなのです。
「行動経済学」を知ることで、「マリッジブルー」になってしまう原因がわかり、そうならないように対策をとれます。
また、パートナーの行動や判断を賛成できなくても、それはパートナーの性格や価値観に問題があるのではなく、「人の行動や判断の法則」が原因だと理解できれば、パートナーにやさしくなれるのです。
いかがですか?
少し興味を持っていただけたでしょうか?
それでは、「マリッジブルー」を「行動経済学」で解き明かして行きましょう。
著者
本書の著者は橋本之克さん。
現在、マーケティングやブランディング戦略のコンサルタント、行動経済学に関する講師、著述家として活動されているそうです。
著書には、「9割の人間は行動経済学のカモである―非合理な心をつかみ、合理的に顧客を動かす」、「9割の損は行動経済学でサケられる―非合理な行動を避け、幸福な人間に変わる」(経済界)などがあります。いずれも行動経済学関係の著書ですね。興味のある方は、是非、読んでみてください。
解釈レベル理論
さて、「マリッジブルー」の原因となる「人の行動や判断の法則」は、「行動経済学」では「解釈レベル理論」と呼ばれるものです。
これは、時間の変化につれて判断や評価が変わる心理的バイアスのことです。
心理的バイアスとは?
ちょっと、難しいことばが出てきましたね。
バイアスというのは「偏り」という意味です。
心理的バイアスというのは、人が何かの行動や判断をする際に、知らず知らずのうちに紛れ込んでしまう偏った見方や考え方のことです。
有名なところでいえば、たとえば、台風災害で危険が身に迫っている状況だったとします。テレビニュースやラジオでどんなに避難勧告をしても避難しない人って多いですよね。
実は避難しない人の多くは、何となく「自分は助かるだろう」と思っているのです。その結果、逃げ遅れて命を落とす人もいます。
「自分は助かるだろう」と考えることには何の根拠もないですよね。危険が迫っていて、避難勧告まで出ているなら、避難することが合理的な判断・行動です。避難しないというのは明らかに不合理な判断・行動です。
この「自分は助かるだろう」と考えるのも心理的バイアスの一つです。知らず知らずのうちにそのような偏った見方や考え方をしてしまうのです。
ちなみに、これは「正常性バイアス」と呼ばれています。
はい。ここまでは大丈夫でしょうか?
解釈レベル理論とは?
では、「解釈レベル理論」に戻ります。
これは、人は、知らず知らずのうちに時間の変化につれて判断や評価を変えてしまう傾向があるという理論です。
どのように判断や評価が変わるかというと、時間的に遠いことについては、より抽象的なレベルで考えるのですが、逆に時間的に近いことについては、より具体的なレベルで考える、というふうに変わるのです。
冷静に考えれば、結婚式を挙げるというだけでも、いつ挙式するか、どこで挙式するか、それぞれ何人を招待するか、だれを招待するか、席順をどうするか、食事をどういうものにするか、引き出物を何にするか、ドレスをどうするか、お色直しを何回するか、だれに挨拶を頼むか、など考えなければならないことはたくさんありますよね。
ところが、結婚を決めた時点では、結婚式まで半年とか1年とかはありますよね。
この段階では、結婚できる幸せを感じ、結婚式で祝福されるイメージなどを漠然と頭の中で思い浮かべている程度で細かいところを考えない傾向があるのです。
これがより抽象的なレベルで考えるということです。具体的で細かいことを考えていないので、新郎・新婦ともに幸せいっぱいです。
そこから、結婚式が時間的に近づくにつれて、より具体的で細かいことを考えるようになり、いろいろな調整が必要になります。パートナーとの意見が合わないところも出てくるのでストレスも溜まります。
だんだん時間がなくなってくるため、焦りから、イライラしてケンカしてしまうこともあるでしょう。そして、物ごとがうまくいかないのは、パートナーのせいではないか、この人と結婚してもうまくいかないのではないか、と将来が不安になり、気分が落ち込んでしまいます。
これが「マリッジブルー」です。
結婚式から時間的に遠い時点では、将来を誓い合い、「この人となら幸せになれる」と思っていたのに、結婚式が近づくと、「この人と結婚してもうまくいかないのではないか」と思ってしまう。
これは、パートナーとの相性が合わないということではないのです。解釈レベル理論による心理的バイアスが、人の判断から一貫性を失わせてしまった結果なのです。
このことを理解しておかないと、自分自身を信じられなくなったり、逆にパートナーに非があると思い込んでしまう可能性があるのです。
「マリッジブルー」対策
「マリッジブルー」の原因が、解釈レベル理論による心理的バイアスにあると理解できれば、そうならないように対策を立てることができますよね。
結婚式から時間的に遠い時点から、より具体的で細かいところも少しずつ考えるようにすれば、結婚式が近づいたころに焦ったり、イライラすることは避けることができます。早めに結婚式場を決めて、担当者と結婚式までに決めなければならないことを相談しながら、少しずつ準備を始めましょう。
![]()
それでも、パートナーとの意見が合わないこともあるかもしれません。そして、パートナーがイライラして攻撃的になってしまうこともあるかもしれません。
そんなときには、「パートナーに非がある」、「この人と結婚してもうまくいかないのではないか」と考えるのではなく、「解釈レベル理論の心理的バイアスがパートナーをイライラさせているんだ。」と考え、パートナーにやさしく接しましょう。
そうすれば、きっと、パートナーが「マリッジブルー」になることを避けられるはずです。
おわりに
さて、いかがでしたでしょうか?
今回は、「解釈レベル理論」しか紹介できませんでしたが、本書には、ほかにもいろいろな場面で「行動経済学」が活用できることが紹介されています。
「行動経済学」は生活からビジネスまであらゆる場面に活用できる実用的な学問ですが、人への理解が深まり、「人にやさしくなれる」学問でもあります。
興味のある方は是非本書を手に取ってみてください。
ではまた。




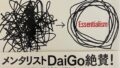
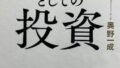
コメント